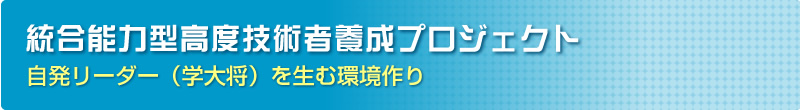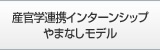知の創造と活用
1B
ナノバイオテクノロジー
担当教員・所属コース等・職
| 担当教員 | 所属コース等 | 職 |
|---|---|---|
| 新森 英之(代表) | 生命工学科(生命環境学部) | 准教授 |
| 楠木 正巳(副代表) | 生命工学科(生命環境学部) | 教授 |
| 大槻 隆司 | 生命工学科(生命環境学部) | 准教授 |
| 小川 和也 | 先端材料理工学科 | 准教授 |
| 野田 悟子 | 生命工学科(生命環境学部) | 准教授 |
| 小久保 晋 | 生命工学科(生命環境学部) | 助教 |
| 中川 洋史 | 生命工学科(生命環境学部) | 助教 |
| 久本 雅嗣 | 地域食物科学科(生命環境学部) | 助教 |
| 山村 英樹 | 生命工学科(生命環境学部) | 助教 |
特徴
自然界における多種多様な生命体は細胞で構成されていますが、さらにミクロな目で見ると、その中身は分子の巧妙な組み合わせによって成り立っています。この事実から最近では、バイオテクノロジー分野において分子スケールであるナノレベルでの設計が重要視されています。
このハウスでは、天然での多彩な生物学的機能の工学的側面に焦点を当て、テクノロジー展開のためのナノレベル解析、機能性材料・センサ設計、バイオマテリアル合成、分子コミュニケーション、光デバイス、分子機械、微生物機能解析等の基礎技術を習得することを目的としています。系統的に準備された実習メニューに取り組むことで、バイオとナノテクとの関連について理解を深めることができます。
キャリアハウス実習後、卒業研究や大学院での先端研究を通じて、ナノバイオテクノロジーに関する統合的能力を持ったエキスパートの養成を目指しています。
キーワード
- 生体機能
- 超分子化学
- センサ
- 機能性ハイブリッド材料
- バイオマテリアル
- 光デバイス
- ナノエレクトロニクス
- 分子機械、
- ナノメカニクス
習得できる知識・技能・精神
[ 知識 ]
- 生命活動の化学的原理
- 生理活性物質の種類と機能
- バイオセンサの原理と種類
- 機能性色素の光化学
- X線構造解析の原理
- 微生物培養工学
- 分子マシンの設計
[ 技能 ]
- 新規化合物の設計・合成技術
- 物質同定に関する構造解析
- 各種分析化学的装置の取り扱い
- 光機能性材料の光化学的特性評価
- 生体関連物質の機能評価
- 微生物培養の手法
- バイオセンサの作製方法
- 分子マシンの機能評価
[ 精神 ]
生命活動の維持はナノレベルで説明が可能であり、有益な材料の手本となる。
将来の展望
生命体の生物学的機能を分子レベルで理解し、人類に役立つ材料創出やシステム開発のできる技術者を目指しましょう。
活動内容の概要
[ 1年次後期 ]
- 生体内における物質の役割を学びます。
- 各種分析機器や培養器具の取り扱いを習得します。
- 生化学に関する基礎的実験を行います。
[ 2年次 ]
- 新規化合物の合成方法を習得します。
- 機能性化合物の物性の評価法を習得します。
- 微生物の培養手法を習得します。
- 高精度ナノレベル分析装置の解析を理解します。
[ 3年次 ]
- タンパク質の結晶構造解析に関する実験を行います。
- 微生物による代謝産物から生理活性成分を分析し、単離精製します。
- 新規光デバイス分子の確立のために、光機能性材料の光化学的特性を評価します。
- 分子マシンのナノレベルでの動きや働きを解析します。
- バイオセンサのシステム化に向けた化学修飾法を習得し、基礎的機能評価を行います
活動風景

機能性化合物の合成方法の習得

機能性化合物の形状特性評価の習得

培養実験法の習得